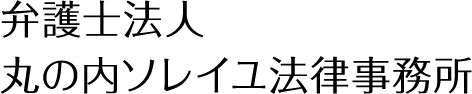外国で亡くなられた方の相続放棄について

事業に失敗した父親が多額の借金を残して亡くなった―このような場合には、相続放棄をして、自らが借金をかぶることを回避したいと考えるのが当然だと思います。
相続放棄は、相続があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった方(被相続人)が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります(民法915条第1項、家事事件手続法201条第1項)。
ここで、被相続人が外国で亡くなった場合はどうなるのでしょうか。多額の借金を残して国外逃亡―あり得ることですよね。
どこの裁判所で手続を行うのか

この点、日本の裁判所は、被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)に管轄権を有するとされています(家事事件手続法第3条の11第1項)。
この規定からすると、日本に居住していた被相続人が旅行中等一時的に外国に行って、そこで亡くなったような場合には、問題なく日本で手続ができますが、外国に居住していた場合には、日本の裁判所では手続ができないことになります。
しかしながら、日本の法律を適用して手続をすべき場合に(この点は次項で説明します。)、外国の裁判所でしか手続ができないとすると、非常に不便ですよね。
そこで、例外的に日本の裁判所で手続を行うことが可能な場合があります(これを緊急管轄が認められると言います。)。
緊急管轄が認められる場合には、基本的に東京家庭裁判所で手続が行われることになりますので(家事事件手続法7条)、東京家庭裁判所に対して、緊急管轄が認められるべきである旨を主張していくことになります。
その際には、単に相続人が日本に居住していて日本の裁判所で手続をすることが便利であるといった主張にとどまらず、外国で手続をした場合に日本と同等の手続をしてもらうことが困難であるということを主張する必要があります。
具体的には、以下の観点から主張・立証をしていくべきであるとされています。
① 被相続人の住所地の国において相続放棄の制度が定められているか否か
② 被相続人の住所地の国において本件における相続人に適用される法(その地の国際私法を適用した後に適用される法)に相続放棄の制度が定められている場合に、本件における相続人が相続放棄を行うことが制度上認められているか否か
③ 被相続人の住所地の国において、本件における相続人に適用される法(その地の国際私法を適用した後に適用される法)に相続放棄の制度が定められている場合に、裁判官による判断によって相続放棄ができない場合があるか否か
④ 被相続人の住所地の国において、本件における相続人に適用される法(その地の国際私法を適用した後に適用される法)に相続放棄の制度が定められている場合に、その効果として債務の免除や最初から相続人でなかったものとすることが認められているか否か(例えば、遺産放棄の効果のみ認められている場合などがあり得る。)
⑤ 被相続人の住所地の国において相続放棄がされた場合において、その放棄が家事事件手続法79条の2によって我が国において効力を有するか否か(例えば、相互の保証がない場合には、我が国において効力は認められない。)
どこの国の法律を適用するのか

日本の裁判所で手続ができるとして、次に問題になるのが、どこの国の法律を適用して手続をするか(準拠法はどこの国の法律か)という問題があります。
この点については、被相続人の本国法を適用するのが原則ですので、被相続人が日本人であれば日本法、韓国人であれば韓国法が適用されることになります。
なお、本稿は外国で亡くなられた方の相続放棄について見てきましたが、外国の方が日本で亡くなられた場合にも日本法が適用される場合があります。上記のとおり、外国の方についてはその方の本国法が適用されるのが原則なのですが、その方の本国法によれば日本法を適用すべき、という場合があるのです(これを反致といいます。)。
例えば、被相続人が中国人の場合、中国法を適用すべきということになりますが、中国法によれば「被相続人の死亡時の常居所地法」を適用すべきとされているため、日本で生活していて日本で死亡した中国人の相続放棄については、死亡時の常居所地法である日本法を適用すべき、ということになります。
まとめ
外国で生活し、外国で亡くなられた方の相続放棄の手続を日本で行うには、日本の裁判所に緊急管轄を認めてもらう必要があります。
そのためには、被相続人が生活していた国の法律を調査した上で、日本の裁判所で手続をする必要があることを裁判所に理解してもらう必要があります。一度専門家である弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
相続でお困りの方は専門家にご相談を

相続が発生したが何から手を付けてよいかわからない!というお客様はお早めに弁護士にご相談ください。
令和6年4月から相続登記の義務化が始まりました。相続を先延ばしにしているとさまざまな問題が後で起きてきますので、相続にご不安を感じている方は、お気軽に弊所にご相談ください。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は2009年創業。当事務所では民事事件を主に取り扱っており、相続に関するご相談には経験豊富な弁護士2名体制でお客様をサポート致します。不動産が絡む相続問題に強みがあり、ご相談だけでなく売却等のお手伝いもしているのが特徴です。
事務所は東京・丸の内にございます。東京駅南口 徒歩4分、東京メトロ千代田線二重橋駅 徒歩1分。
丸の内ビルディング、丸の内仲通りすぐそばの好立地ということで、お買い物やお仕事帰りのお客様にも多くご利用頂いております。

弊所の弁護士費用は、3ヶ月間定額料金で法律相談が可能なバックアッププラン(5.5万円)、弁護士が代理人となる紛争解決サポートなど、お客様のお費用感に合わせたプランがございます。
詳しくは下のリンクから弁護士費用ページをご覧いただくか、初回の無料相談(60分)をご利用ください。