
認知症だった父や母が亡くなった後、生前に遺言書を残していたことが明らかになった場合に、遺産の相続手続は、遺言書の内容に沿って進めなければならないのでしょうか。
1.認知症の人がした遺言は有効か?
そもそも、認知症だからといって、その遺言が必ずしも無効になるとは限りません。遺言をするには、自分が行う遺言の内容や意味を理解し、そこから導かれる結果を理解することのできる「遺言能力」が必要とされています。すなわち、認知症だったとしても、その程度が軽度で、遺言の内容を十分に理解できているのであれば、その遺言は有効です。
また、認知症の程度が進行し、後見開始の審判がなされて成年後見人がついている場合であっても、遺言能力が一定程度回復していれば、遺言書を作成することが可能です。この場合には、医師2人以上の立会いが必要とされています(民法973条)。なお、後見人が選任されている場合に、後見の計算が終了する前に後見人やその配偶者、子、孫などの直系卑属に利益となる遺言をしたときは、遺言能力の有無にかかわらず無効となります(民法966条)。
2.認知症の親がした遺言が無効または取消になり得るケース

⑴ 最低限の意思能力すら失われている状態でなされた場合
認知症が進行し、意思能力が失われて遺言の意味も認識できないような状態で作成された場合は、その遺言は無効となります。たとえば、本人が寝たきり状態で発話もできず、日常生活も介助がなければ送れないような場合は、不動産や預貯金などの重要な財産について、誰に何をどのように残すか細かく指定する遺言を行う能力はなかったと考えられることから、無効と判断される可能性が高くなります。
なお、過去の裁判例では、公証役場において公証人に作成してもらった「公正証書遺言」でも、作成当時に本人が意思能力を欠いていたとして無効と判断された例もあります。
⑵ 周囲が遺言を偽造・変造した場合
たとえ本人には遺言書を作成できる程度の意思能力があったとしても、本人は遺言書を書いていない(あるいは文字を書けない)のに、同居の親族が本人名義で勝手に遺言書を偽造したり、本人に無断で遺言書を書き換えて変造したりした場合は、偽造・変造された遺言は無効となります。特に本人が認知症の場合、本人では遺言書を適切に管理することができないため、管理を任されている同居の親族が、本人の遺言書を偽造・変造したりするケースが散見されます。
⑶ 詐欺・強迫によって遺言が作成された場合
認知症の親と子の家族が同居していて、子やその配偶者などの親族が本人に対して詐欺や強迫を行い、本人の意思に反して無理やり遺言書を書かせたような場合には、そのようにして作成された遺言は、無効ではないものの、詐欺や脅迫により作成されたことを主張立証して取り消すことができます。
3.遺言が無効である場合に相続人がとりうる対応

認知症の親が残した遺言が無効である場合には、裁判所において遺言が無効であることを確認してもらう必要があります。そのためには、まずは遺言無効確認調停を申し立て、そこで調停が調わなければ、遺言無効確認訴訟を提起しなければなりません。
⑴ 遺言無効確認調停
これは、家庭裁判所において、裁判官や調停委員の関与の下、遺言の有効性について他の相続人と話し合うための手続です。遺言が無効であることについて、関係者間で話合いが折り合わなければ、まずは遺言無効確認調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条1項、調停前置主義)。この調停で、相手方が遺言を無効とすることに納得すれば、遺言が無効であることが確認されますが、納得しない場合には、調停は不成立となって終了します。
なお、事前に関係者間での話合いが調わなかったからこそ、裁判手続を利用するに至っていることも多いため、調停を申し立てず最初から後述する遺言無効確認訴訟を提起しても、裁判所の判断で調停に付さずにそのまま訴訟手続が進められることもあります(家事事件手続法257条2項但書)。
⑵ 遺言無効確認訴訟
これは、地方裁判所において遺言が無効であることの確認を求める訴訟手続です。遺言無効確認調停が不成立で終了すれば、この訴訟を提起することが可能となります。訴訟の相手方となる被告は、遺言が有効であると主張している相続人や受遺者ですが、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者となります。
この訴訟では、遺言が無効となる原因事実を主張立証しなければなりません。たとえば、遺言能力の欠如を理由に遺言が無効であることを立証する場合には、遺言書の記載内容や、カルテや診断書などの医療記録・介護記録、証人尋問の結果などが証拠となります。残された遺言書が自筆証書遺言の場合、筆跡鑑定が行われることもあります。これらの主張立証に成功すると、裁判所から遺言が無効であることを確認する判決が下されます。その結果、遺言は効力を有しないため、法定相続人や受遺者などが遺産分割協議を行い、遺産の分割方法を決定することになります。
なお、遺言無効確認訴訟には時効はなく、いつでも提訴することは可能ですが、時期が遅れると無効であることの証明が難しくなったり、相続財産が失われてしまう可能性が高まるので、遺言が無効であると考えるなら早めに裁判手続をとることをお勧めします。また、遺言無効確認調停の申立てから始まり、遺言無効確認訴訟の提起、無効確認後の遺産分割までを含めると、全ての相続手続が終了するまでに相当長い時間がかかります。
4.遺言無効確認訴訟を提起する場合に、事前に揃えておいた方がよい資料

遺言の無効確認を求める場合、提訴前に、以下のような資料を揃えておきましょう。
⑴ 認知症だった被相続人の医療記録や介護記録
遺言書を作成した当時、亡くなった父や母には既に遺言能力が失われていたため、遺言が無効であると主張する場合には、遺言当時の被相続人の状態を主張立証する必要があります。そのため、病院からは医療記録(カルテ、診断書)や看護記録、介護施設からは介護記録を取り寄せると共に、要介護認定の資料(要介護認定を受けた際の主治医の意見書の控え、認定調査票など)も探しておきましょう。
⑵ 長谷川式簡易知能評価スケール
認知症の有無や程度を計る指標として「長谷川式簡易知能評価スケール」が使われることも多いです。長谷川式簡易知能評価スケールは、30点満点で、21点以上が正常、20点以下は認知症の疑いがあるとされており、点数が低くければ低いほど、認知症の程度が高いとされます。すなわち、この点数が低いと、遺言能力が疑わしいとされる可能性があります。
したがって、医療記録等においてこの点数が書かれた資料があれば、それも確保しておきましょう。
⑶ 筆跡鑑定
認知症だった被相続人の遺言書で、同居していた親族が遺言を偽造・変造したことが疑われる場合には、本人以外の者によって遺言書が書かれたことを証明するため、筆跡鑑定を行います。筆跡鑑定には、被相続人が実際に書いた文字と遺言書の文字を比較する必要があるため、被相続人が実際に書いた文字が含まれる資料を探しておきましょう。また、余力があれば、提訴前に筆跡鑑定を依頼し、鑑定評価書をもらっておきましょう。
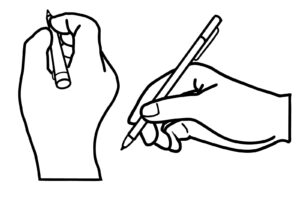
5.まとめ
このように、認知症だった父や母が残した遺言に納得できない場合は、遺言書を作成した当時の認知症の程度や遺言書の内容に応じて、遺言無効確認調停や訴訟で争い、遺言が無効であると判断してもらう方法があります。もっとも、仮に無効と確認された後も、相続人や受遺者の間で一から遺産分割協議を行って遺産を分割しなければならず、このときに遺産の評価や分割方法を巡って再度争いになることも多く、争いが長期にわたることが多いです。






